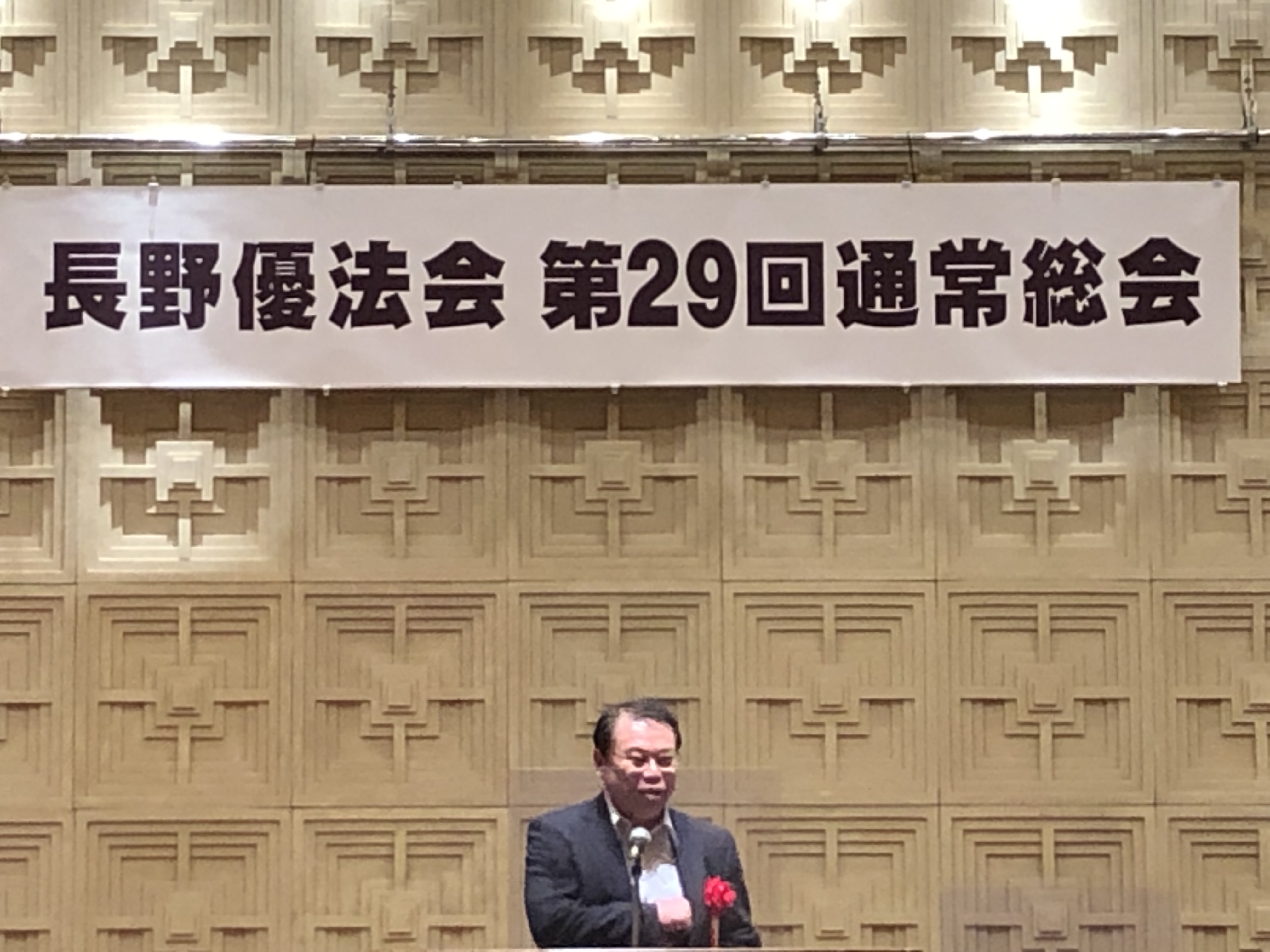令和3年度長野県経営者協会長野支部総会が開催された。令和2年度の事業報告と令和3年度の事業計画。コロナ禍であるので、令和2年度がほとんど事業ができず、令和3年度は状況を見て実施ということになる。本会の事業活動本心に沿って支部も活動をしていく。今年度こそ、「会長を囲む経営懇談会」が実施されるといいなあ~と個人的に思っている。
総会後の記念講話は、山浦愛幸・本開名誉会長が「生糸産業が創った長野県産業」という演題で、八十二銀行誕生の歴史も含めての内容であった。
1873年に第一国立銀行が設立され1879年に国立銀行設立停止になるまでに153の国立銀行が設立された。現在の八十二銀行は、1877年に上田町(上田市)に設立された第十九国立銀行と1878年に松代町(長野市)に設立された第六十三国立銀行が1931年8月1日に合併して八十二銀行になった。2021年8月1日は90周年記念日である。生糸業が盛んな頃は、マユが銀行の担保権であり、諏訪倉庫で眉を保管したという話も興味深かった。