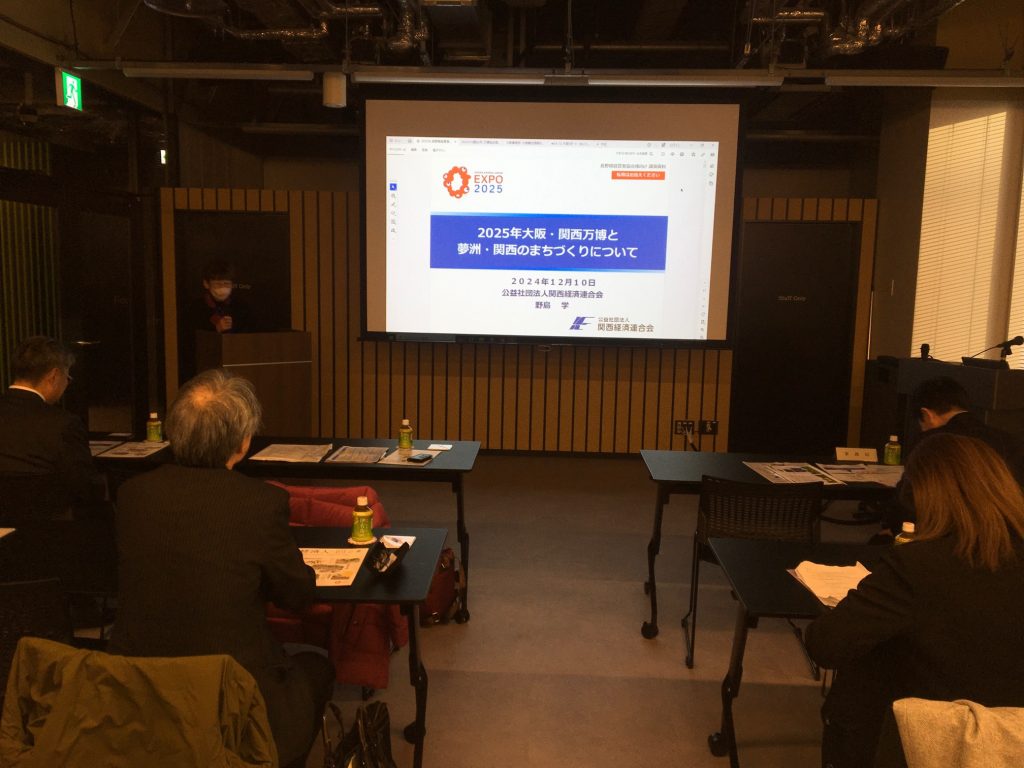日経懇話会第6回例会講演会は、「海外リスクから事業と社員をどう守る?~地政学リスクの高まりと企業の対応」という演題で、コントロール・リスクス・グループ株式会社代表取締役岡部貴士氏からの講演であった。
経営者が直面する可能性のある地政学リスクを特定し、リスク管理戦略的対応についてのアプローチを教えてもらった。
2025年のリスクマップがあり、各地域の無事ネスリスク環境が色別に区分されている。リスクが極めて高く、今後もその状態が続くため、通常のビジネスは困難とされている国は、ロシア連邦、ウクライナ、北朝鮮、スーダン、中央アフリカ、イエメン、イラン、アフガニスタンほかである。
分断する世界に企業はどう備えるべきかという観点では、重要な視点を3つ挙げられた。
1 シナリオ分析とストレステストの重要性。ありえそうなシナリオだけでなく、「ブラックスワン」に対するストレステストも必要で、これは実施しているとしていないとの格差は大とのこと。
2 プリンシプルベースの自社の「意味」を再確認。想定外の事態は必ず起こることの想定を持つことが必要。
3 「戦後」の新秩序への回帰まで織り込んだ中長期的な対応事例からの示唆。要するに、分断化する世界や世界大戦を生き延び、戦後も発展し続けた企業の事例には示唆があるそうだ。
今まで、このような危機管理に気が付いていなかった。一つの情報として、必要とするクライアントに提供していく必要性を感じている。