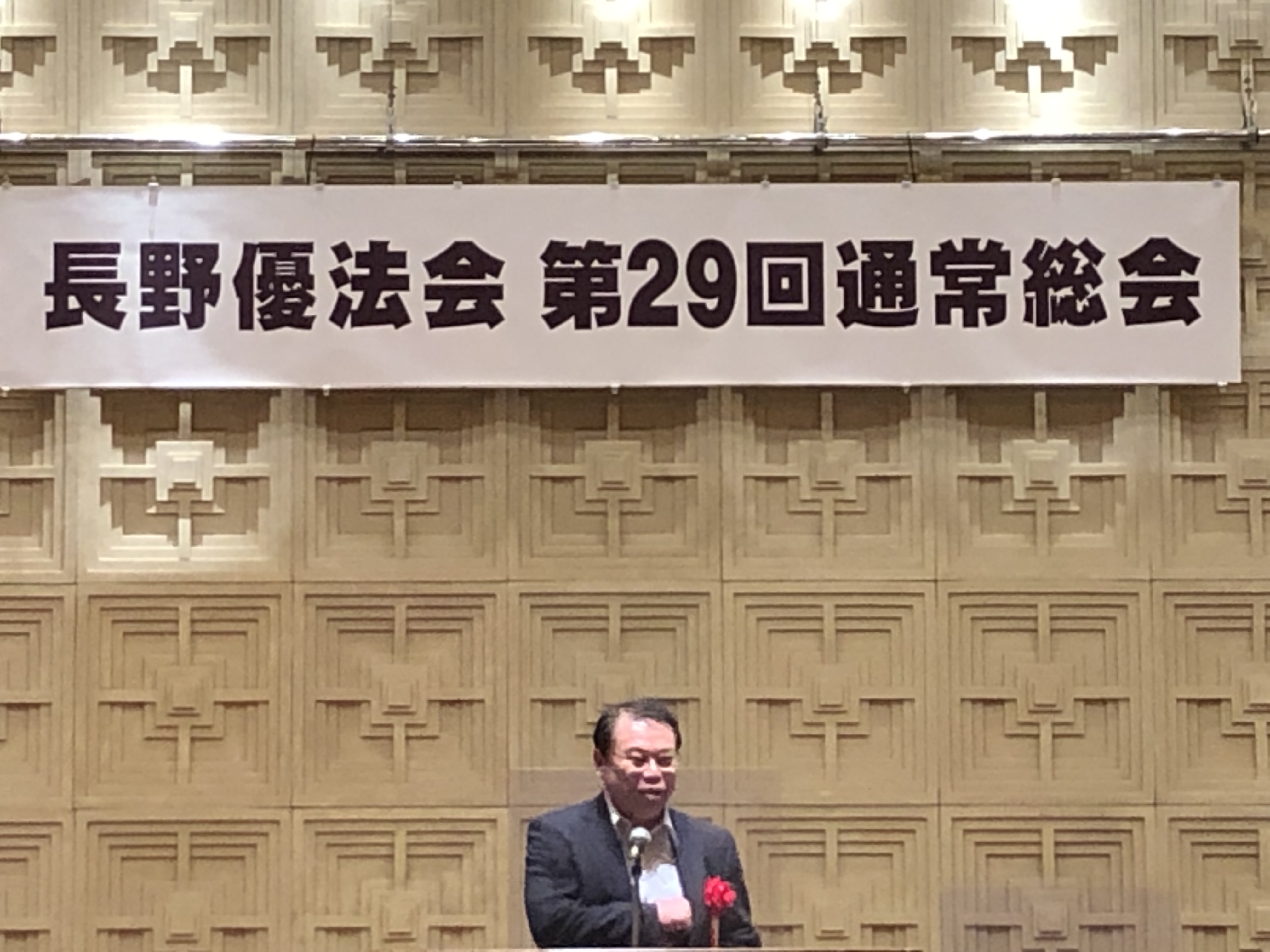みんなで支える森林づくり県民会議が開催された。今年度第1回目の開催であり、令和2年度森林づくり県民税活用事業の実施状況についての報告があった。
現在森林税が導入されてから1期5年で2期終了の2017年度までの10年間は、里山での間伐を中心に森林づくりを進めてきた。現在は第3期目の4年目(令和3年度)に入っており、里山整備のほかに多面的に森林の利活用に使途を広げている。第2期が終了する時点で問題になった森林税基金残高も令和22年度末では358,938千円になった。1年間の森林税収入は6.8億円。森林税は令和4年度までの継続であり、令和4年度末には基金残高が0となる見込みだ。それまでにまた森林税の在り方を検討するのだろう。
里山整備事業においては、予算の執行はおおむね計画通りだが、整備面積においては、第3期目標値が4,300haであるのに対し40%の1,726haしか実施されていない。「整備面積は予算の関係があり伸び悩んでいる」という県の説明があったが、森林税活用事業の要である里山整備事業なので、ならば今後どうしていくかの説明がもっと欲しかった。
森林税の使途の認知度は38%。長野県県政モニターアンケート調査の結果ということである。
山を守る、森林を守るために森林税を活用したたくさんの事業が行われているが、もう一歩環境に踏み込んだ議論ができるといいなあ~というも感じている。
山奥に残されたワイヤーはどうするのか、鳥獣被害防止のための防護柵を設置しているが、倒壊してもそのままになっている現状、ならば生分解性製品を利用したウッドガードを積極的に利用することにより、さらに森林が生き返るのではないか・・・と思っている。